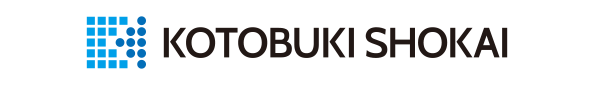Claris Engage 2025 の2日目。
今日は、朝からテクニカルセッション目白押し。今日は休憩という概念はありません!
Do More With Execute FileMaker Data API
「FileMaker Data APIを実行」スクリプトステップにフォーカスしたセッション。
比較的小さな会場だったため、セッションの途中や終了後に活発に質問が出ていました。
このような特異なケースにどのようなエラーが出るのか、など具体的な質問が多く出ていて、参加者にはこの機能のヘビーユーザーも多い印象でした。スピーカーが実証できていない部分については、会場からも知見が提供されて、活発なやりとりが行われました。
データの編集機能(create, update, delete, duplicate)への対応は比較的新しいため、これから細かなノウハウが蓄積されることを期待したいです。
(このトピックに興味がある方には、同内容のCommunity Liveについて、以前のブログ記事でも触れています)
Community Live 18: 「FileMaker Data APIを実行」スクリプトステップ – 最速レビュー
Making The Business Case for AI
最初にスピーカーのCrisさんのAIとの関わりが紹介され、2020年頃のGPT-3を使ったプロトタイプなどが示された後、2つのユースケースが、ユーザ企業側の担当者の方から紹介されました。
1つは3Mの事例で、まずFileMakerによるプロンプトの効率的な管理方法についての説明がありました。
また、AIを活用した法律文書の作成、翻訳用途での可能性が示されました。
もう一つは、求人者と求職者のマッチングの例でした。去年のEngageでのAIセッションを見てiSolutionsとの協業を決めたとのことでした。その後の実業務でのAI機能を活用した求人活動の中で、AIによる履歴書の選別で職を得た人がその後すぐに辞めてしまったという失敗事例から、すべての判断をAIを行うのではなく、例えば、AIで広く絞り込んだ後に人の判断も含めたプロセスに改良したそうで、AI活用でよく聞かれるHuman in the loopという考え方が示されました。
Transform how you collect and share external data with internal teams through Claris Studio
Claris FileMaker は主に内部向けアプリケーション、Claris Connect は連携と自動化、そして Claris Studio は外部向けソリューションというのが役割という話は以前からの通り。「 FileMaker の皆さんが愛する精神、つまり顧客の要求の変化に迅速に対応できるという点を Claris Studio でも維持したい」という方向性は安心するところ。
技術的なところでは、FileMakerとの連携における3つのデータ連携方法(シャドウテーブル、Claris Connect、ダイレクトデータソース)について説明があり、Studio と FileMaker 間のリアルタイムなデータ同期のデモンストレーションがありました。また、細かいけども実際に利用するには必要になってくる新機能についても紹介されました。
個人的には FileMaker での動的値一覧のような選択肢は Google フォームではできないので、例えばFileMakerに登録済みの日時は選択肢に出てこないようにする受付のフォームなどは Studio ならではの使い方になる。
不特定多数の大規模ユーザーにも耐えられるように作られているものの、プレビュー状態が外れた正式版のときに明かされるライセンス体系についてははっきりしていないのが気になっている。
How to build well-architected solutions in Claris FileMaker
well-architected は、堅牢でスケーラブルな FileMaker ソリューションのために、評価プロセスとチェックリストをまとめましょうといった概念。まず最初にそれを評価したり改善計画を記録管理するツールが紹介されていました。しかしこのツールを使えさえすればできるというものではなく、この概念を管理して記録するツールといった位置づけなので、ちょっと期待していた「スピーカーのSoliant Consultingの評価ノウハウが知れる」ものではなかった。
後半はバックアップについての考察。通常のバックアップにもハードリンクの利用や並列バックアップ、プログレッシブバックアップ、ディスクのスナップショットなど、利用可能なバックアップ方法を活かすために、どのようにファイル分割するかを詳しく解説していました。また、バックアップのためのファイル分割ではなく、疎結合のためのファイル分割のススメという話もあり、リードレプリカ的な冗長構成の場合の同期方法についても触れられていた。
大規模ソリューションの経験はなかなか得られるものではないだけに、いい話が聞けた。
Under the hood: Claris FileMaker Server and WebDirect
Engage のみんな大好き Under the hood。今回はほとんどが次の新バージョンについての話だったので、ほとんどが NDA 。AI などの派手な新機能だけでなく、WebDirect の機能強化、パフォーマンス向上への数々の修正、Let’s Encrypt 証明書管理、など新バージョンが出たらすぐアップグレードすべき理由が数多く紹介された。
冒頭に「退屈なサーバーは完璧なサーバーである」という Duncan Baker 氏の言葉を引用して、安定性と信頼性が最優先事項と強調していました。最近はサーバーに新機能がいくつも求められる中でもやはり最優先はそれだよねと安心。
新バージョンではなく最近リリースされた 21.1.3 の話はして大丈夫だと思うのですが、サーバー上のスクリプト実行やスケジュールによるスクリプト実行を行ういわゆる FMSE エンジンのメモリーリークの解消と同時に機能強化がされました。これと同時に効率的に並行処理されるようになっているとのことでした。
これまでサーバーのスペックを上げてもスピードが上がらないという話がよくありましたけど、高負荷時のスピードはサーバーのスペックを上げるとそれ相応のスピードになるとのことなので今度時間があれば比較ブログを書いてみたい。
AI and Claris Fireside Chat: Transforming how we build
ClarisとAIの今後についてパネリストと参加者が語り合うセッション。
まずClarisの技術者から、LLMを使ってFileMakerデータのSQL検索を実現する新機能について、開発時の苦労や工夫について紹介されました。関連して、FileMaker用のSQLをどう学習させるかについて、参加者との意見交換が行われました。
後半は、FileMakerやStudio、Connectの開発をAIでどう自動化するかについて、将来の可能性が議論されました。
要望として、FileMakerレイアウトを自動的にStudioレイアウトに変換できないか、Claris Connectのカスタムコネクターを自動作成できないか、などの要望が出されていました。
また、将来に向けてAI対応が進む中、今できることとして、設計に関する情報をLLMが理解しやすくするよう、あらゆるものにわかりやすい命名規則を採用することが挙げられていました。例えば、後で意味が解読不明な省略形を使わない、などです。考え方としては、AIはとても優秀な新人スタッフだと考えること。彼は会社のルールを何も知らないが、ちゃんと素材があれば、彼は正しく推測できる、ということです。
From Soup To Structure: Leveraging Large Language Models for Structured Data Extraction
LLMを使って、自然文などの非構造化データを、例えばデータベースへ格納できるような構造化データに変換するという考え方が示されました。
ポイントとしては、LLMが普及しても構造化されたデータの重要性は今までと変わらないこと。LLMはその特性として必ずハルシネーションがあるもので、それをどう検知して、なくすかの工夫が求められるということでした。
LLMのハルシネーションをLLMで防ぐということは(少なくとも今は)できず、Entropy、Jaccard Indexなどの従来からあるテクニックを活用する例がデモされました。
Under the hood: AI in Claris FileMaker
Engage のみんな大好き Under the hood。今回はすべてが次の新バージョンについての話だったのでNDA。
ただこれだけは伝えたい。次の新バージョンは「 AI するなら FileMaker ! 」と言えるぐらい大進化する ことを。
現状でも様々なクラウドサービスや Web API 連携を使えば、かなりのことが AI でできる時代ではある。しかし1つの結果を得るにはいろんな前処理や便利な Web API へ複数リクエストして結果を得る必要があるのが現状。それがローコードツール Claris FileMaker ならいとも簡単に、という世界が始まります。現在の FileMaker Developer にとって開発が楽になる、それはつまり利用ユーザーが最新の AI 活用を当たり前のように使える世界です。この1時間のセッションスライドは事前配布版でも193ページもあり、このページ数からも新バージョンの AI 新機能の豊富さが伝わると思います。
このセッション後は1時間ぐらい興奮冷めやまぬという感じで、一緒にセッションを聞いた日本の参加者とすごいよね〜、これぞ DevCon だね〜、なんて話し合ってました。